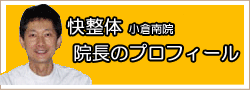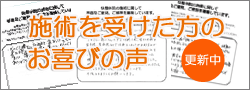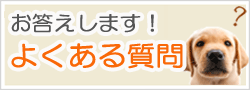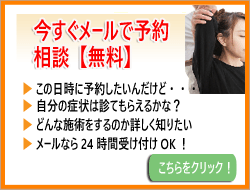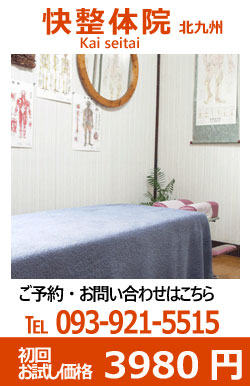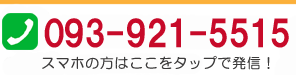筋肉を鍛えても肩こりや痛みは解消しない?
肩こりや肩の痛みに悩む人は多く、それを解消しようとマッサージや整体、鍼灸に通う人も少なくありません。しかし、一時的に症状が和らぐことはあっても、根本的に治るケースは少ないものです。そこで、「運動不足が原因では?」と考え、筋肉を鍛えれば解決すると信じる人もいます。
しかし、「使わない筋肉が緩む」という考えは誤解です。筋肉は、使いすぎると張りや痛みの原因になることはあっても、使わないからといって弛緩するわけではありません。実際、じっとしている時間が長い人ほど、筋肉は硬直しやすくなります。これは、日常的に重力や姿勢の維持によって筋肉が緊張し続けているからです。病気や宇宙空間など極端な環境で長期間動けない場合を除けば、普通に生活している人の筋肉は、使わないからといって衰えるのではなく、むしろ収縮して硬くなっていくのです。
長時間同じ姿勢を続けた後、「体が緩んで困る」と感じる人はいないでしょう。それは、静止していても筋肉には一定の負荷がかかり続けているからです。特に悪い姿勢を長時間続けることで、一部の筋肉に過度な負担がかかり、肩こりや腰痛が生じます。
こうした症状を改善しようとジムに通い、ハードなトレーニングを始める人もいますが、実はこれが逆効果になることも。激しい筋トレは筋肉に強い負荷をかけ、さらに収縮を助長します。その結果、筋肉はますます硬直し、肩こりや痛みが悪化する可能性があります。
もちろん、適度な運動は体に良い影響を与えます。しかし、強い筋トレや長距離の水泳、不適切なストレッチは、むしろ凝りや痛みの原因を悪化させることもあります。特に、痛みの解消を目的にした運動であれば、その方法を慎重に選ぶべきです。
肩こりや痛みのメカニズムを考えると、多くの人は「筋肉が固まっているから」と思いがちですが、実際には筋肉のバランスが崩れていることが主な原因です。
現代人の生活はパソコン作業などで前かがみの姿勢が多くなりがちですが、その結果、胸の筋肉(大胸筋)は縮み、肩や背中の筋肉(僧帽筋)は伸びた状態になります。この状態が続くと、僧帽筋は元に戻ろうとして緊張し、張りや痛みを引き起こします。一方、大胸筋は縮んだままで硬くなっているため、全体のバランスが崩れたままになります。
このように、筋肉は単独で動くのではなく、拮抗する筋肉とのバランスによって機能しています。特定の筋肉だけを鍛えたりほぐしたりするのではなく、全体のバランスを整えることが重要なのです。
体のバランスを整えるには、過度な筋トレではなく、適切なストレッチや軽い運動が有効です。特に、筋トレの際には筋肉痛が残らない程度の強度を意識し、ストレッチでは筋肉の裏表をリセットすることが重要です。
ストレッチといっても、単に筋肉を伸ばすだけではなく、適切な方法で行う必要があります。例えば、肩こり解消のために僧帽筋だけをマッサージしても、大胸筋の緊張を解かない限りバランスは崩れたままです。そのため、裏表の筋肉両方にアプローチする必要があります。
また、ランニングやジョギングは運動として良いですが、無理に取り入れる必要はありません。むしろ、ウォーキングなどの軽い運動の方が、凝りや痛みの改善には適している場合が多いのです。
日常でできるセルフチェック
体のバランスを整えるためには、まず自分の体の状態を知ることが重要です。特に、前後左右のバランスが崩れていないかをチェックする習慣をつけると良いでしょう。
例えば、以下のようなチェックを行うと、自分の体のバランスの崩れに気づくことができます。
• 鏡の前で立ち、自分の体が左右どちらかに傾いていないか確認する
• 両手を上げたとき、どちらかが高くなっていないかを見る
• 靴底の減り方を確認し、偏りがないかをチェックする
意識的に体のバランスを確認することで、自分の姿勢の癖や偏りに気づきやすくなります。そして、その改善を意識することで、凝りや痛みの軽減につながるのです。
まとめ
肩こりや痛みを解消するためには、単に筋肉を鍛えるのではなく、筋肉のバランスを整えることが重要です。過度な筋トレはかえって症状を悪化させることもあるため、適度な運動やストレッチを取り入れることが推奨されます。
また、自分の体のバランスをチェックし、日常生活で姿勢を意識することも効果的です。前後左右のバランスを整えることが、凝りや痛みの根本的な解決につながるのです。